10月13日はサツマイモの日。
10月がサツマイモの旬でさつま芋の別名「十三里」にかけて制定されたものです。
ちなみに制定したのはさつま芋愛好会の「川越いも友の会」とのこと。
川越の名産品ですね、さつま芋。
「土壌がさつま芋に合っている」って農家の人が言っていたのを今でも覚えています。
でも実際あんまり埼玉県産のさつま芋食べた記憶がないですが・・・
農林水産省のウェブサイトを見ると埼玉は5位以内にも入っていません。
やっぱり鹿児島と茨城ですよね・・・
でも川越の名産品として、さつま芋を見てみたいと思います。
川越いもの特徴と特長
なんで「十三里」っていわれるの?
まずなぜ「十三里」なのかというと
・産地である川越がだいたい江戸から「十三里」(約51km)だったことが一つ。
・「栗よりうまい」にかけて「九里四里うまい」で「十三里」としたことが一つ。
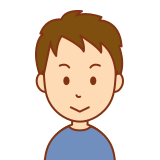
ようは洒落ですね
「川越いも」ってどんないも?
川越でさつま芋の栽培が普及し始めたのは18世紀半ばのころ
現在の所沢市で今の千葉県から種芋を取り入れて栽培したのが始まりとのことが川越市のウェブサイトに詳しく載っています。
もちろん所沢市にも記念碑があるので散歩がてら足を運んでみるのもいいかもしれません。
現在の千葉県では青木昆陽によって既にさつま芋の栽培が確立されていました。
実際今でも千葉県は国内有数のさつま芋産地です。
そんな「所沢で始まったいも栽培」が、なぜ「川越いも」になったか。
それは「将軍、徳川家治に貰った名前」だから。
川越藩主の松平直恒が川越地方でとれたさつま芋を献上したところ由来しますが、それだけ川越の名前が大きかったからともいえます。舟運の力は大きい。
どんなさつま芋が作られているの?
今、名産となっているさつま芋は「紅赤」というさつま芋です。
これも浦和で偶然発見されたさつま芋なんですけれど、川越地方(現・三芳町)でしか栽培に適さなかったことから、川越いもとして残っています。
食べた感じはどんなもの?
味は甘みがあるものの、そこまで強くありません。
それよりも粉雪のような舌触りと栗のような香りが特長です。
火の通りも早いので調理にも向いています。
詳しくは詳しくは川越市のウェブサイトに情報が載っています。
面白いので是非ご覧ください。
どこで作られているの?
やはり有名な産地は入間郡三芳町ですね。
三芳町では「富の川越いも」としてブランド化してふるさと納税の返礼品にもなっています。
また、現在では川越市でもさいたま市でも栽培されています。
技術の進歩はすごいですね。
どんな食べ方があるの?
紅赤のおススメ
「紅赤」に限って言えば調理がおススメですので天ぷらやきんとんが向いています。
もちろん他にもいろんな食べ方があります。
お菓子
いもようかんやいもせんべいなどほかにもスイートポテトやいもまんじゅうなどいろいろな食べ方があります。
和菓子屋さんもさつま芋を推しているところが多いですね。

お酒
「紅赤」と聞いて思い出したのが発泡酒という人も多いのではないでしょうか。
地ビールとして地元ではよく見かけるCOEDOビールの一つですね。
やはりこちらも三芳町のふるさと納税返礼品になっています。
吞んだ感じは「芋ビールだ!」と唸らざるを得ません。
さつま芋の甘みとビールのキレが見事にマッチしていて新感覚の味わいがそこに待っています。
20歳超えていてお酒の飲める人はぜひ口にしてみて下さい、今までにない不思議なおいしさがありますよ。
その他
有名な所では「いも御膳」や「いも定食」があります。
他にもきっとあなた好みの食べ方があると思います。
まとめ
今日は「サツマイモの日」ということで川越いもの紹介をしました。
個人的にはいも菓子と紅赤(酒)のイメージが強い川越いもですが、いかがでしょうか?
個人的には所沢で始まり浦和で見つかった品種を三芳で栽培して売り出した川越いもの流れが面白く感じました。

なぜ、その名前になる?
でも海外ミュージシャンが「さいたまスーパーアリーナ」で「ハロー,トーキョー!!」と言っているようなものかと感じました。
江戸時代の地理感覚なんて同じようなものなのでしょう。
最後に、川越のさつま芋お菓子はおいしいものが多いのでおススメです。
もし観光に行く機会があったら是非食べてみてください。
そろそろ観光客でいっぱいになると思います。
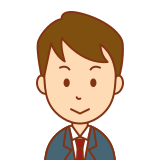
この機会に食べ歩きはいかがでしょうか?
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ご感想などがあれば、是非コメント欄に書き込んでもらえると幸いです。
Twitterもやっているので、そちらに書き込んでいただいても嬉しいです。
またよろしくお願いします😊
誤字や脱字の報告も大変喜んでお待ちしております。



コメント